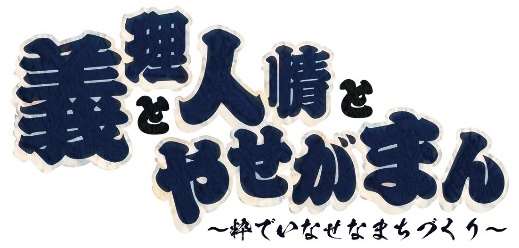

第61 代理事長 瀧澤 智英
~はじめに〜
私は幼いころ「将来の夢は」と言われヘルメットを被った作業員の絵をかきました。な ぜそのような思いを抱いたのかと考えると、毎日作業着を着て出ていく父や、祖父の姿を 見て育ったからだと思います。やはり子供は親や身内の背中を見て将来を思い描くものな のだと思います。そんなことからか、私は中学校を卒業後すぐに鳶職人の道へと歩み始め、 後に起業を果たし今もなお生業として生きています。戦国の世が終わり平和をもたらした 江戸時代は、まちも賑わい沢山の木造建築が建ち並びました。鳶職人たちは当時その建築 工事をおこなった職人たちを束ねたり、木造建築が多く隣接するまちでは火事がとても多 くその火消し作業も職人やまちの若者を束ねて行ったそうです。そんな鳶職人たちの中で 「義理と人情とやせがまん」という言葉が生まれ今なお当時の木遣り・纏・梯子のぼりと 共に受け継がれています。私もこの言葉を受け継ぎ、とても大事にしている言葉です。私 は目で見てやりたいことをやり、体験して自分の進むべき道を見つけ沢山のことを感じて 生きてきました。私たちの世代はそういったことが多い時代でしたが、現代はソーシャル ネットワークの普及により時代の流れは一気に加速し続けています。今や幼い子供達でも スマートフォンを持ち自由に情報を得ることのできる時代になり、親の背を見ること以外 にも沢山の夢を描ける世の中へと変化してきています。そんな中私たちはどんな姿を今の 子供たちに見せ、どんな未来へ導いていけるのでしょうか。
戦後焼け野原になったこの日本を再建させるべく集まった青年たちが青年会議所を発足 させて、その運動が瞬く間に全国へと波及していきました。1965 年には高田と直江津の二 つの青年会議所が合併して上越青年会議所が発足し、昨年度60 周年を迎えました。当時の 先輩諸兄姉は今の上越を想像しながら運動を行ってきたのでしょうか。思い返せば「あの 時の運動が今につながっている。」ということが沢山あるはずです。今の上越があるのは 紛れもなく各時代に未来を想い描き運動をし続けてきたからであり、その運動は止まるこ となく60 年間続いてきました。その節目を迎え今年度は次の新時代へ進む第一歩を踏み出 します。
近年、利便性の多い社会で、人との関りはどんどんと希薄しているように感じます。私 は人と人の繋がりが何をするにも大事だと思います。「天の時は地の利に如かず地の利は 人の和に如かず」どんなに利便性が良く整ったものがあっても人心の一致団結にはかなわ ないという言葉で、こんな時代だからこそとても大事なことだと私は強く思っています。 私たちにできること、私たちにしかできないことが青年会議所にはあります。先輩諸兄姉 が未来を想い描き成し遂げてきた運動を私たちも引継ぎ後者へと繋いでいきます。今日の 運動が未来を変えていくように、子供たちにも誇れる未来を想い描き、行動できる若者が 社会を変える力を持っていると信じ、「変わったのではない、変えたのだと誇れる未来へ」 さぁ、まちづくりを始めよう。
~組織の形・組織の一員として~
時代と共に組織の形は年々変化を遂げています。5 年前に比べると会員数は100 名規模 から50 名規模へと大きく減少し、所属メンバーも小規模事業者や、サラリーマンも増えて きました。近年では家族や、子育ての時間と両立して活動できる仕組みを推進する動きが あり、上越青年会議所も組織の在り方を変えていく必要があります。社業・家族・プライ ベート・JC 全てを大事にしてほしい。だからこそ、やるときにみんなできちんとやる。そ うでないときは他のことにきちんと時間を使う。時間とお金がなければやれない組織では なく、どんな人でもどんな役職もできるような組織づくりを目指します。だからこそメン バー一人ひとりが役割をはたし、誰かだけがやるのではなく、みんなでやり遂げる組織で なければいけません。社会の最小単位は家族であり、家族や会社の犠牲の上に明るい豊か な社会は成り立ちません。働き方改革が生まれたように、JC も少ない時間でも効率良く、 中身の厚い運動や活動を展開できるようにする必要があります。そのためには、決められ た人だけが行う組織ではなく所属メンバー全員で取り組み、すべての会員が「家族・会 社・地域のために」と誇れる組織へと改革していこう。
~ブランディング力と会員拡大~
会員拡大は青年会議所発足以来、唯一の継続事業であり、青年会議所の最重要な運動で す。メンバーの精力的な拡大は、事業の波及効果を高め、青年会議所運動を加速させる重 要なピースです。なぜなら、人が人へと発信、伝達していくことが、青年会議所運動への 賛同を得るきっかけになり、仲間が増えればより広域で効果的な発信へとつながるからで す。これからも青年会議所運動を発展させていくためには、より多くの人財が必要不可欠 です。近年は地域の人口減少に伴い、組織の人員減少は青年会議所だけではなく、各団体 や各企業も抱える大きな課題です。そんな中、人員獲得の手法として組織のブランディン グ力が重要です。今やSNS 発信は一部の若者だけではなく行政や各企業も取り入れており、 活用方法によってとても大きな効果を見込めます。まずは今まで行っている発信方法を見 直すことと、効果的な取り組みによって上越青年会議所の活動や運動を発信し会員拡大へとつなげていきます。更に近年の拡大成功事例に基づき拡大方法や仕掛けの仕組みを作り 直すことと、担当者だけでなくメンバー全員が動き総合力で拡大目標25 名を必達とし、持 続可能な組織であり続けなければならない。
~組織運営と基盤強化~
円滑な組織運営を行うために、まずは執行部で決定する事項を素早く共有し会全体へ発 信していくことで進む方向を常に明確にしていきます。組織を円滑に運営するためには、 必ず裏方仕事が必要となっていきます。それはまさしく縁の下の力持ちであり組織を支え る要のポジションです。円滑な会議の設営や、対外事業への参画補助を行い、メンバーが また参加したいと思う運営をしていきます。各種事業への参加での学びや交流を通じて横 の繋がりを深めることや、真剣に意見交換する場を創出することで、互いを高め合える仲 間づくりと熱量の高い組織の構築へとつなげます。
財政面では公益社団法人として、地域の負託と信頼を得る組織であるためには法令遵守 はもちろん財務の健全化や透明化をしっかりと行い、基盤を整えて進む必要があります。 更に、OB 会員・現役会員・賛助会員との絆を強固にし地域に良き理解者、協力者を増やし ていきます。近年は会員減少に伴い財源に苦しむ状況が続いていますが、今後も継続して いけるような運営や仕掛けを確立していきます。メンバーが円滑に活動できるように運営 と財務管理を行い、健全な組織であることが必要である。
~LOM の原動力と会員交流~
「会員交流委員会はLOM の花形だ」私は今までの歴代の会員交流委員会を見てきてそう 確信しています。なぜこの委員会はこのように受け継がれて来たのか。それはいつもメン バーの中心には会員交流委員会がいて、それはLOM の大きな原動力となり、メンバー同士 の団結力、元気の源であったからです。人が人に寄り添い、メンバーに対する見返りのな い奉仕の気持ちがいつもパワーをくれる存在でした。「振り向けばいつもあいつらがいる。」 そんな存在が私の理想とする会員交流委員会です。近年の例会参加率は70%を切ることも あり、月に一度メンバー全員が集う例会に約30%ものメンバーが参加しない状況が続いて います。この状況ではLOM のベクトル共有や団結力が低下していってしまいます。我々が 入会の時に言われた、「毎月の例会と委員会は必ず参加」を今一度全メンバーに再認識し てもらい、年間例会参加率90%以上を必達します。参加する例会は学びや交流のある機会 とし、LOM のベクトルを共有する場とします。参加メンバーには青年経済人としてふさわ しい例会参加の仕方を追及していきます。「人心の一致団結が強国を作る」というように 年間を通してメンバー同士が交流する機会を創出し強固な組織づくりへとつなげます。こ の先も力強く活動・運動ができる組織になることが我々の使命である。
~上越の魅力を国内外へと発信~
上越は、四季を体感できる豊かで素晴らしい自然に囲まれ、また、歴史的文化も数多く 存在する風情溢れる地域です。高田の観桜会、謙信公祭、越後・謙信SAKE まつりなど多く の県内外客が参加するビッグイベントも地域特有の文化・歴史があるからこそ誕生したも のです。上越市は中心部に広がる高田平野を取り囲むように中山間地域が広がり、冬期に は大陸からの季節風の影響により多量の降雪があり、ほぼ全域が特別豪雪地帯に指定され ています。この雪深い地域に都市が発達したことは珍しい例で、こうした自然環境は古来 より当地の人々の暮らしを支え、発展の礎となってきました。今日の豊かな風土や生活文 化は、雄大で厳しい自然環境との共生を図り豊穣な海や山がもたらす恩恵を受けることに よって育まれてきたと言えます。雪がもたらす恩恵を再認識し、国内外へと発信すること で、上越の魅力を波及していこう。
~妙高の魅力を上越と共に~
妙高市には日本を代表する自然風景地の指定や日本百名山の3 座が市域にあり、その自 然環境に沢山の動物や植物が生息しています。自然の恵みである七五三の湯と呼ばれる温 泉や山岳信仰などに源を発する歴史・文化があり、その風土は妙高の自然の恵みとともに あり、地域固有の食文化、工芸なども育んできた地域です。自然の美しさとアウトドアア クティビティが豊富で、歴史的・文化的にも魅力を持つエリアで、四季を通じて訪れる価 値がある観光地として、多くの人に親しまれています。そんな妙高市が「消滅可能性自治 体」に該当されたこの状況は決して他人事ではなくいつか上越にも訪れるかもしれない大 きな地域課題です。こんな時だからこそ隣接市との連携を強固にしていくことが大切だと 思います。自分たちだけで何とかする選択よりも、連携するパートナーを作り、その関係 をより強固なものにし、「妙高の魅力を上越と共に。」そんな新しい運動を創りだそう。
~垣根を越えて~
近年では、少子高齢化・人口減少・都市部への生産年齢人口の流出などによって大きな 打撃を受けています。2050 年までの30 年間で若年女性人口が半数以下になり、最終的に 消滅する可能性がある「消滅可能性自治体」は全国で744 あり、県内では30 市町村の6 割 にあたる18 市町村が該当します。その中には隣接市の妙高市も含まれます。この問題は上 越市にとっても他人事ではない地域課題で、毎年浮上する人口減少問題は行政も対策をし ていますが、未だ歯止めが利かない状況です。同じ課題を抱える地域同士、個々に課題に 取り組んでいくのではなく互いに手を取り合うことで我々が住むまちを守り、よりよくし ていく選択はできないだろうか。上越・妙高地域が垣根を越えて、互いの魅力を伝える事 業を共同で行い、両市民が集えば今までよりももっと広域な市民へ運動が波及し、互いを 理解し手を取り合えば今までよりももっと大きな効果が生まれるはずです。両市民が共同 してくことへの共感が増せば新しい未来の形が生まれるかもしれない。2015 年には北陸新 幹線が開通され上越妙高駅が誕生しました。それを見て私はいつか上越妙高市が誕生する のではないかと想い描きました。新しい未来を創るなど、理想だと笑う人もいるかもしれ ません。でも、理想が無ければ人生という航海を羅針盤なしに進むのと同じです。どれだ け否定されようと、理想を語り達成すると使命感を持ち行動することが、未来を創るとい うことなのです。私たちの小さな一歩がいつしか未来を変えたと言えるように、何かが起 こることを待つのではなく、未来を創ることを選択し、そのための一歩を踏み出そう。
~結びに~
「義理と人情とやせがまん」この言葉は300 年も昔から受け継がれてきた言葉で、道理 を通して、人を思いやり、それを果たすために少しだけ自分を犠牲にすること。私もずっ と大事にしてきている言葉です。何かを成し遂げたいとき一人では厳しいかもしれないけ れど、誰かと一緒なら成し遂げられることも沢山あると思います。私たちはどこかで必ず 誰かに助けられながら生きています。だからこそ人へ感謝し人とのつながりがとても大事 です。持ちつ持たれつ、まずは自分から相手への思いやりをもって人とのつながりを大事 にしてほしいです。まちづくりは人が行うものでそこに集う人が多ければ多いほど大きな 波及が生まれます。人と人がつながり集まればまちができ、まちとまちがつながれば文化 が生まれます。
人は何かを成し遂げた時に感動します。未来へ続くロードを照らし続け、これからの未 来を想い描き、市民と共にまちづくりをしていこう。無理かもって思ったらもうそれより 先になんて進めない。方法は無限大、可能性は永遠の海。やれそうって思ったらもうほと んどは乗り越えたようなもの。我々にしかできないことがある。我々だからできることが ある。限界を越えて、粋でいなせなまちをつくろう。
公益社団法人上越青年会議所 事務局025-522-1819受付時間 10:00-15:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ お気軽にお問い合わせください。